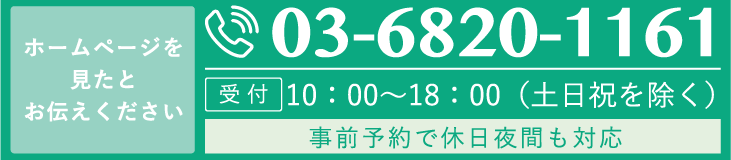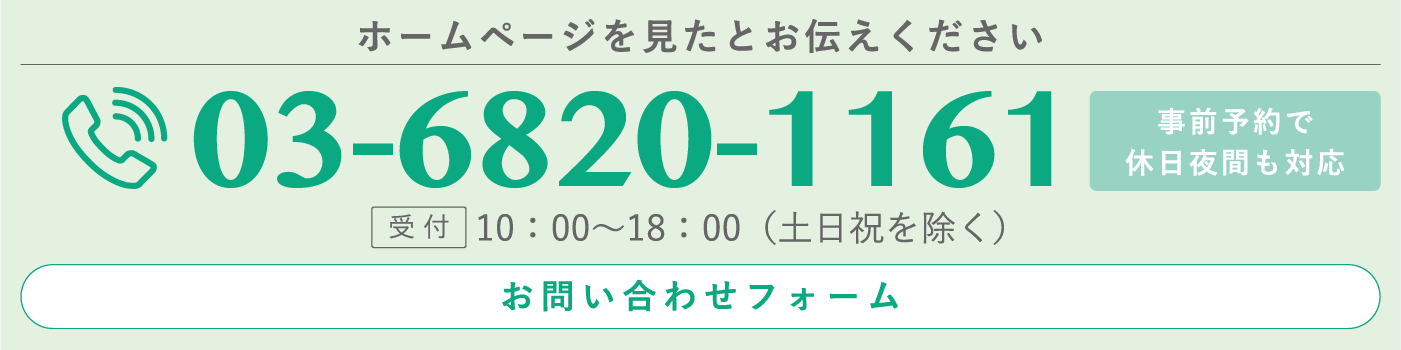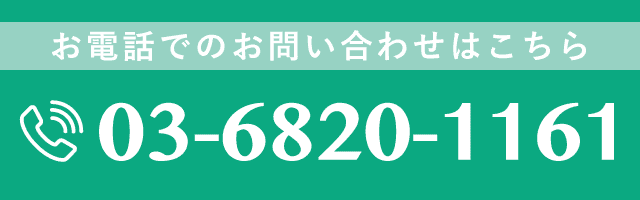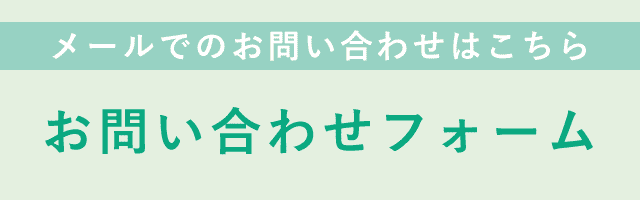Author Archive
未来トレンド研究機構に弁護士林邦彦のインタビュー記事が掲載されました。
株式会社未来トレンド研究機構に弁護士林邦彦の「健康食品業界におけるNo.1表記・初表記」に関するインタビュー記事が掲載されましたのでお知らせ致します。
【インタビュー記事が掲載されているウェブサイト】
https://espers.co.jp/original-interview/16911/

弁護士 林 邦彦は、企業法務の中でも特に専門性の高い2分野、健康・美容関連商品の広告規制法務と、ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務を得意としております。
薬機法や景品表示法の複雑な規制、あるいはBSAやACCSからの突然の警告といった、企業の存続に関わる重大な問題に対し、約8年間の豊富な経験と深い知見に基づいて、高度で良質なリーガルサービスを提供いたします。
ご相談から問題解決まで、弁護士が一貫して担当し、貴社にとって最善の結果を追求します。
遠方の方でもウェブ会議に対応可能です。 貴社のビジネスの「安心」を全力でサポートいたします。
秘密厳守。お問い合わせを心よりお待ちしております。
薬機法違反の摘発事例(ペットフード関連)
薬機法は、ペット用の健康食品・サプリメントの広告において、疾病の治療又は予防を目的とする効能効果(医薬品的な効能効果)を標ぼうすることを禁止しています。
そのため、ペット用の健康食品・サプリメントの広告において疾病に対する効能効果を標ぼうすると薬機法違反に該当し、懲役や罰金といった刑事罰が科される可能性があります。また、その捜査の過程で逮捕や捜索差押をされる可能性もあります(ペット用の健康食品・サプリメントの広告規制については「ペットフード・ペット用(動物用)健康食品・サプリメントの広告に関する無料法律相談」というページでご説明していますのでご参照ください)。
そこで、ペット用の健康食品・サプリメントの広告に関する摘発事例を以下ご紹介します。
犬猫用サプリメントの通販等を行う会社(以下「A社」といいます)が「ガンや疾病の予防に」などと広告してペット用のサプリメントを販売していたところ、大阪府警が同社の社長を薬機法第55条(未承認医薬品の販売・授与)違反と同法第68条(未承認医薬品等の広告の禁止)違反の容疑で逮捕しました。
A社は、上記サプリメントを延べ1300人(リピート顧客を含む)に販売して約2000万円を売り上げており、同社の顧客の中にはペットがガンであり治療目的で利用していた方もいたようです。
また、A社は、過去に少なくとも2回神奈川県から薬機法違反で行政指導も受けていたようです。
まとめ
上記事例のように、(人間用の健康食品・サプリメントではない)動物用の健康食品・サプリメントの広告においても薬機法の摘発がされていますので、注意が必要です。
私は、これまでサプリメントなどの健康食品、ペットフードを取り扱っている会社・個人事業主の方から広告に関するご相談を多くお受けしており、これらの商品の広告規制に関する厚生労働省・消費者庁・都道府県・消費者団体への対応や刑事弁護の案件も取り扱ってきました。
ペットフード・ペット用(動物用)健康食品・サプリメントの販売や広告作成を行っている企業の方からの広告に関するご相談は、ウェブ会議によるご相談を初回1時間無料でお受けしております(東京だけではなく、全国対応可能です)。
ご希望される場合は問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。
※初回無料相談は企業の方からのご相談に限らせていただいております。個人の方からの初回のご相談は30分当たり1万1000円(税込)の費用がかかります。

弁護士 林 邦彦は、企業法務の中でも特に専門性の高い2分野、健康・美容関連商品の広告規制法務と、ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務を得意としております。
薬機法や景品表示法の複雑な規制、あるいはBSAやACCSからの突然の警告といった、企業の存続に関わる重大な問題に対し、約8年間の豊富な経験と深い知見に基づいて、高度で良質なリーガルサービスを提供いたします。
ご相談から問題解決まで、弁護士が一貫して担当し、貴社にとって最善の結果を追求します。
遠方の方でもウェブ会議に対応可能です。 貴社のビジネスの「安心」を全力でサポートいたします。
秘密厳守。お問い合わせを心よりお待ちしております。
ダッソーシステムズによる和解の最新事例紹介(2022年12月公表)
新聞報道によると、北海道の研究機関は、同機関の従業員がダッソー・システムズ・ソリッドワークス社(以下「ダッソーシステムズ」といいます)の図面設計ソフトの海賊版をインストールして利用していたことが判明し、その後同機関とダッソーシステムズとの間で和解交渉を行った結果、8300万円の損害賠償金を支払う旨の和解が成立したと記者会見で発表しました。
上記報道によると、上記従業員は、インターネットでダッソーシステムズの図面設計ソフトの海賊版を入手し、2018年から職場や私物の複数パソコンに海賊版をインストールして利用していたところ、2022年8月にダッソーシステムズから上記機関に対する通知により当該不正インストールが発覚したようです。
私は、これまで数十社からソフトウェア不正利用の損害賠償対応に関する案件のご相談をお受けしており、その豊富な知識と経験に基づき、ダッソーシステムズへの対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてダッソーシステムズとの交渉を行うことが可能です。
ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。また、ウェブ会議や電話によるご相談も対応しておりますので、遠方の企業の方のご相談に対応させていただくことも可能です。
ウェブ会議によるご相談を初回1時間無料でお受けしております(東京だけではなく、全国対応可能です)。

弁護士 林 邦彦は、企業法務の中でも特に専門性の高い2分野、健康・美容関連商品の広告規制法務と、ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務を得意としております。
薬機法や景品表示法の複雑な規制、あるいはBSAやACCSからの突然の警告といった、企業の存続に関わる重大な問題に対し、約8年間の豊富な経験と深い知見に基づいて、高度で良質なリーガルサービスを提供いたします。
ご相談から問題解決まで、弁護士が一貫して担当し、貴社にとって最善の結果を追求します。
遠方の方でもウェブ会議に対応可能です。 貴社のビジネスの「安心」を全力でサポートいたします。
秘密厳守。お問い合わせを心よりお待ちしております。
BSA会員による証拠保全の事例紹介(2009年~2014年)
BSAのウェブサイト等で公表されているソフトウェアの不正利用に関してBSAの会員企業が証拠保全の申立てを行った事例をご紹介します(BSAについては「ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務」というページでご説明していますのでご参照ください)。
1.熊本市所在のメディア業者の事例
- 証拠保全の申立時期
2014年2月 - 裁判所
熊本地方裁判所 - 権利者(会員企業)
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの違法コピーに関する情報の提供があったため、上記権利者が上記業者に対してソフトウェアのインストール状況及びライセンスの取得状況の調査を依頼しましたが、上記会社から何ら回答がなかったことから、上記権利者は証拠保全の申立を行いました。
2.大阪府所在の広告業者の事例
- 証拠保全の申立時期
2013年1月 - 裁判所
大阪地方裁判所 - 権利者(会員企業)
マイクロソフト コーポレーション
アドビ システムズ インコーポレーテッド - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの違法コピーに関する情報の提供があったため、上記権利者が上記業者に対してソフトウェアのインストール状況及びライセンスの取得状況の調査を依頼しましたが、上記会社から具体的な調査結果を伴う回答がなかったことから、上記権利者は証拠保全の申立を行いました。
3.静岡県所在の食品販売業者の事例
- 証拠保全の申立時期
2012年4月 - 裁判所
静岡地方裁判所 - 権利者(会員企業)
マイクロソフト コーポレーション
アドビ システムズ インコーポレーテッド - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの違法コピーに関する情報の提供があったため、上記権利者が上記業者に対してソフトウェアのインストール状況及びライセンスの取得状況の調査を依頼しましたが、上記会社から具体的な調査結果を伴う回答がなかったことから、上記権利者は証拠保全の申立を行いました。
4.栃木県所在のメーカーの事例
- 証拠保全の申立時期
2012年1月 - 裁判所
宇都宮地方裁判所栃木支部 - 権利者(会員企業)
マイクロソフト コーポレーション
オートデスク インク
アドビ システムズ インコーポレーテッド
ダッソー・システムズ・ソリッドワークス・コーポレーション - 事案の概要
BSAに違法コピーの実態に関する詳細な情報が寄せられ、また上記メーカーにおいて役員が組織内違法コピーを主導していたことが推測されたことから、上記権利者は証拠保全の申立を行いました。
5.東京都所在の旅行会社の事例
- 証拠保全の申立時期
2009年8月 - 裁判所
東京地方裁判所 - 権利者(会員企業)
アドビ システムズ
ファイルメーカー
マイクロソフト - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの違法コピーに関する情報の提供があったため、上記権利者が上記業者に対してソフトウェアのインストール状況の調査を依頼しましたが、上記会社は具体的な調査結果を伴う回答がないばかりか証拠隠滅等のおそれがあったことから、上記権利者は証拠保全の申立を行いました。
A対応に関する案件に多く携わった経験があり、BSAへの対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてBSAとの交渉を行うことが可能です。ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

弁護士 林 邦彦は、企業法務の中でも特に専門性の高い2分野、健康・美容関連商品の広告規制法務と、ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務を得意としております。
薬機法や景品表示法の複雑な規制、あるいはBSAやACCSからの突然の警告といった、企業の存続に関わる重大な問題に対し、約8年間の豊富な経験と深い知見に基づいて、高度で良質なリーガルサービスを提供いたします。
ご相談から問題解決まで、弁護士が一貫して担当し、貴社にとって最善の結果を追求します。
遠方の方でもウェブ会議に対応可能です。 貴社のビジネスの「安心」を全力でサポートいたします。
秘密厳守。お問い合わせを心よりお待ちしております。
BSA会員による証拠保全の事例紹介(2005年~2008年)
BSAのウェブサイト等で公表されているソフトウェアの不正利用に関してBSAの会員企業が証拠保全の申立てを行った事例をご紹介します(BSAについては「ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務」というページでご説明していますのでご参照ください)。
1.滋賀県所在の電気機器メーカーの事例
- 証拠保全の申立時期
2008年5月 - 裁判所
大津地方裁判所 - 権利者(会員企業)
オートデスク インク
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAの通報窓口に提供されたソフトウェアの違法コピーに関する情報に基づき上記権利者が証拠保全の申立を行いました。
私は、これまでBSA対応に関する案件に多く携わった経験があり、BSAへの対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてBSAとの交渉を行うことが可能です。ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

弁護士 林 邦彦は、企業法務の中でも特に専門性の高い2分野、健康・美容関連商品の広告規制法務と、ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務を得意としております。
薬機法や景品表示法の複雑な規制、あるいはBSAやACCSからの突然の警告といった、企業の存続に関わる重大な問題に対し、約8年間の豊富な経験と深い知見に基づいて、高度で良質なリーガルサービスを提供いたします。
ご相談から問題解決まで、弁護士が一貫して担当し、貴社にとって最善の結果を追求します。
遠方の方でもウェブ会議に対応可能です。 貴社のビジネスの「安心」を全力でサポートいたします。
秘密厳守。お問い合わせを心よりお待ちしております。
ソフトウェアの不正利用に関する裁判例紹介(ダッソー システムズ/アペックス事件)
ソフトウェアの不正利用に関する裁判例である東京地裁平成19年3月16日判決(ダッソー システムズ/アペックス事件)をご紹介します。
なお、上記判決の全文は、裁判所のウェブサイトに掲載されています。
1.当事者
- 原告(ソフトウェアメーカー)
ダッソー システムズ - 被告(不正利用者)
デザインモデル等の製作会社
2.事案の概要
被告の従業員がダッソーシステムズのソフトウェアである「CATIA」を違法なクラックソフトを用いて改変し、すべてのモジュール(許諾を受けていないモジュールを含む)を使用できる状態にした事案です。
証拠保全手続きにおいて上記改変行為が行われている事実が確認されたことから、原告は、改変されたプログラム等の使用差止め及び廃棄並びに不法行為に基づく損害賠償を請求する訴訟を東京地裁に提起しました。
3.当事者の主張
この訴訟では(1)翻案権侵害の有無、(2)過失相殺類似の抗弁の成否、(3)原告の損害額が主要な争点となり、(2)及び(3)の争点に関して、原告と被告は、それぞれ以下のような主張をしました。
過失相殺類似の抗弁の成否
(1)被告の主張
- ひとたび改変が行われた場合に損害額は巨額なものとなるソフトウェアについては、原告においても容易に改変できないシステムにする等の防止策を採ることも十分可能であったものであり、民法第722条第2項の過失相殺を類推し、算出された損害額のうちの3割のみを被告の負担する損害額とすべきである。
原告の損害額
(1)原告の主張
- 被告は、本件改変行為又はその後の本件読み出し行為によって、本件ソフトウェアに含まれる使用許諾を受けていないモジュールが使用可能な状態を得たものであり、使用可能となった本件ソフトウェアのすべてのモジュールのライセンス料相当額につき利益を受けた。
したがって、著作権法114条2項に基づき、原告は、当該ライセンス料相当額の損害を受けたものと推定される。
(2)被告の主張
- 著作権法114条3項による損害額は、本件改変行為によって使用可能となり、かつ、現実に使用したモジュールのみについて算定すべきである。
- 被告がエンドユーザとして支払うべき金額(小売り価格)ではなく、原告が受けるべき金額(卸売価格)で損害額は算定されるべきである。
4.裁判所の判断
東京地裁は、以下のとおり判断した上で、被告に対して、改変されたプログラム等の使用差止め及び廃棄を命じるとともに、①使用可能となった本件ソフトウェア全体の使用許諾料相当額から本件使用許諾契約に基づく支払額を控除した金額(総額約15億1400万円)、②弁護士費用(総額7500万円)、③遅延損害金の支払いを命じました。
過失相殺類似の抗弁の成否
- 被告従業員による本件改変行為が故意によるものであるところ、容易に改変できないシステムにしなかったこと等の事情をもって、犯罪の挑発行為と同視することはできないから、被告の過失相殺類似の抗弁は理由がない。
原告の損害額
(1)原告の主張について
- 被告は、本件改変行為により、本件使用許諾契約で使用許諾された範囲を超えて、11台の各コンピュータで、すべてのモジュールを使用でき、かつ、本件ソフトウェアを同時に使用できるようにしたものであるから、著作権法114条3項の適用による損害額は、11台につき使用可能となった本件ソフトウェア全体の使用許諾料相当額を算定し、それから本件使用許諾契約に基づく支払額を控除して算定すべきである。
(2)被告の主張
- 著作権法は、その後の使用の有無を問わず、複製権侵害行為や翻案権侵害が行われた時点で著作権侵害行為が成立するとの立場を採っている。さらに、実際のソフトウェアのライセンス契約も、その後の使用の有無を問わず、ソフトウェアの入った媒体の売買契約やオンラインでのダウンロードの行われた時点で代金額が確定するものであり、使用の都度、時間等に応じて課金されるものはごく少数であると認められる。よって、被告の本件改変行為によって使用可能となり、かつ、現実に使用したモジュールのみについて損害額を算定すべきであるという主張は採用することができない。
- 原告が現実に行っているライセンスが第三者を介在させたサブライセンスの形態であるとしても、著作権法第114条第3項の損害の算定は、原告が直接被告とライセンス契約を行う場合を想定して行うことができると解されるから、被告の小売り価格ではなく卸価格で損害額を算定されるべきであるという主張は採用することができない。
5.まとめ
ダッソーシステムズのソフトウェアである「CATIA」を違法なクラックソフトを用いて改変し、すべてのモジュールを使用できる状態にした事例において、使用可能となったソフトウェア全体の使用許諾料相当額に基づき損害額認定された実例として参考になる事案です。
私は、これまで数十社からソフトウェア不正利用の損害賠償対応に関する案件のご相談をお受けしており、その豊富な知識と経験に基づき、ダッソーシステムズ等のソフトウェアメーカーへの対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてソフトウェアメーカーとの交渉を行うことが可能です。
ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。また、ウェブ会議や電話によるご相談も対応しておりますので、遠方の企業の方のご相談に対応させていただくことも可能です。
ウェブ会議によるご相談を初回1時間無料でお受けしております(東京だけではなく、全国対応可能です)。

弁護士 林 邦彦は、企業法務の中でも特に専門性の高い2分野、健康・美容関連商品の広告規制法務と、ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務を得意としております。
薬機法や景品表示法の複雑な規制、あるいはBSAやACCSからの突然の警告といった、企業の存続に関わる重大な問題に対し、約8年間の豊富な経験と深い知見に基づいて、高度で良質なリーガルサービスを提供いたします。
ご相談から問題解決まで、弁護士が一貫して担当し、貴社にとって最善の結果を追求します。
遠方の方でもウェブ会議に対応可能です。 貴社のビジネスの「安心」を全力でサポートいたします。
秘密厳守。お問い合わせを心よりお待ちしております。
BSA会員による調停の最新事例紹介(2022年5月公表)
BSAのウェブサイトによると、BSAの会員であるオートデスク株式会社(以下「オートデスク」といいます)が2021年10月に大阪簡易裁判所に対して調停の申立てを行い、その後相手方である大阪府内の土木工事業者がオートデスクの違法コピー数を認めて、損害賠償金を支払う旨の調停が成立したようです(BSAについては「ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務」というページでご説明していますのでご参照ください)。
上記サイトによると、BSAの通報窓口に上記業者においてソフトウェアの不正コピーが行われているという情報の提供があったため、BSAが上記業者に対してソフトウェアのインストール状況やライセンスの保有状況の調査を依頼しました。
その後、上記業者による調査結果を踏まえて、オートデスクと上記業者との間で損害賠償の交渉を行いましたが、和解交渉がまとまらなかったため調停申立てが行われたとのことです。
調停手続きにおいて、上記業者はライセンスが存在することを主張したものの、提出した証拠は保有しているプログラムがクラックプログラムであることを示すものに過ぎなかったため、最終的に、上記のとおり上記業者が違法コピー数を認めて、損害賠償金を支払う旨の調停が成立することに至ったようです。
私は、これまでBSA対応に関する案件に多く携わった経験があり、BSAへの対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてBSAとの交渉を行うことが可能です。ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

弁護士 林 邦彦は、企業法務の中でも特に専門性の高い2分野、健康・美容関連商品の広告規制法務と、ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務を得意としております。
薬機法や景品表示法の複雑な規制、あるいはBSAやACCSからの突然の警告といった、企業の存続に関わる重大な問題に対し、約8年間の豊富な経験と深い知見に基づいて、高度で良質なリーガルサービスを提供いたします。
ご相談から問題解決まで、弁護士が一貫して担当し、貴社にとって最善の結果を追求します。
遠方の方でもウェブ会議に対応可能です。 貴社のビジネスの「安心」を全力でサポートいたします。
秘密厳守。お問い合わせを心よりお待ちしております。
BSA会員による証拠保全の事例紹介(2015年以降)
BSAのウェブサイト等で公表されているソフトウェアの不正利用に関してBSAの会員企業が証拠保全の申立てを行った事例をご紹介します(BSAについては「ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務」というページでご説明していますのでご参照ください)。
1.福岡県小倉市所在のメーカーの事例
- 証拠保全の申立時期
2022年1月 - 裁判所
福岡地方裁判所小倉支部 - 権利者(会員企業)
オートデスク インク
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAは相手先であるメーカーがオートデスクの製品を違法にコピーしているという情報を事前に入手しており、実際に、証拠保全において裁判所が検証手続きを行った結果、上記メーカーのパソコンに複数の非正規のオートデスクの製品が存在しており、さらにBSAが上記メーカーに調査を依頼した直後に多くのオートデスクの製品が削除された履歴があることが確認されたとのことです。
なお、オートデスク製品の複製・削除状況を検証する際には、オートデスクが提供したスクリプトプログラムを用いて、相手方のパソコンにおけるオートデスク製品のコピー状況や履歴を調査しました。
2.宮城県所在の設計会社の事例
- 証拠保全の申立時期
2017年4月 - 裁判所
宮城県内の裁判所 - 権利者(会員企業)
オートデスク インク
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの無断複製が行われているという情報の提供があり、実際に、証拠保全において裁判所が検証手続きを行った結果、上記権利者のソフトウェアが無断複製が行われており、一部のソフトウェアについては商用利用が認められていないアカデミックパックを使用した無断複製が行われていることが確認されました。
なお、オートデスク製品の複製・削除状況を検証する際には、オートデスクが作成したインストール状況を調べるプログラムを使用して検証が実施されました。 - 証拠保全後の状況
証拠保全後に和解交渉が行われた結果、2017年8月に正規品価格の合計額を上回る総額3000万円で和解が成立しました。
3.熊本県所在の機械製造業者の事例
- 証拠保全の申立時期
2017年4月 - 裁判所
熊本地方裁判所 - 権利者(会員企業)
オートデスク インク - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの無断複製が行われているという情報の提供があったため、上記権利者が上記業者に対してソフトウェアのインストール状況の調査を依頼しましたが、同製造業者の調査結果はBSAに寄せられた情報と大幅に乖離するものであったため、上記権利者は証拠保全の申立を行いました。
なお、オートデスク製品の複製・削除状況を検証する際には、オートデスクが作成したインストール状況を調べるプログラムを使用して検証が実施されました。
4.三重県所在の会社の事例
- 証拠保全の申立時期
2016年2月 - 裁判所
津地方裁判所 - 権利者(会員企業)
オートデスク インク
アドビ システムズ インコーポレイテッド
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAの通報窓口に「AutoCAD」、「AutoCAD LT」、「Microsoft Office」、「Adobe Acrobat」ソフトウェアの無断複製が行われているという情報の提供があったことを端緒として、上記権利者が証拠保全の申立を行いました。
5.京都府所在の酒類販売業者の事例
- 証拠保全の申立時期
2015年6月 - 裁判所
京都地方裁判所 - 権利者(会員企業)
アドビ システムズ インコーポレイテッド
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの無断複製が行われているという情報の提供があったため、上記権利者が上記業者に対してソフトウェアのインストール状況の調査を依頼しましたが、上記業者は一切回答しなかったため、上記権利者は証拠保全の申立を行いました。
私は、これまでBSA対応に関する案件に多く携わった経験があり、BSAへの対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてBSAとの交渉を行うことが可能です。ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

弁護士 林 邦彦は、企業法務の中でも特に専門性の高い2分野、健康・美容関連商品の広告規制法務と、ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務を得意としております。
薬機法や景品表示法の複雑な規制、あるいはBSAやACCSからの突然の警告といった、企業の存続に関わる重大な問題に対し、約8年間の豊富な経験と深い知見に基づいて、高度で良質なリーガルサービスを提供いたします。
ご相談から問題解決まで、弁護士が一貫して担当し、貴社にとって最善の結果を追求します。
遠方の方でもウェブ会議に対応可能です。 貴社のビジネスの「安心」を全力でサポートいたします。
秘密厳守。お問い合わせを心よりお待ちしております。
BSA会員による調停の事例紹介(2017年以降)
BSAのウェブサイト等で公表されているソフトウェアの不正利用に関するBSAの会員企業が調停の申立てを行った事例をご紹介します(BSAについては「ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務」というページでご説明していますのでご参照ください)。
1.大阪府所在の土木工事業者の事例
- 調停申立時期
2021年10月 - 裁判所
大阪簡易裁判所 - 権利者(会員企業)
オートデスク インク - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの不正コピーが行われているという情報の提供があったため、上記権利者が上記事業者に対してソフトウェアのインストール状況やライセンスの保有状況の調査を依頼しました。
その後、土木工事業者による調査結果を踏まえて、権利者と当該事業者との間で損害賠償の交渉を行いましたが、和解交渉がまとまりませんでした。
そこで、2021年10月に上記権利者が大阪簡易裁判所に調停の申し立てを行い、その後調停が成立しました。
2.福井県所在の設備事業者の事例
- 調停申立時期
2021年2月 - 裁判所
福井簡易裁判所 - 権利者(会員企業)
オートデスク インク - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの不正コピーが行われているという情報の提供があったため、上記権利者が上記事業者に対してソフトウェアのインストール状況やライセンスの保有状況の調査を依頼しました。
その後、設備事業者による調査結果を踏まえて、権利者と当該事業者との間で損害賠償の交渉を行いましたが、和解交渉がまとまりませんでした。
そこで、上記権利者が福井簡易裁判所に調停の申し立てを行い、2021年9月に調停が成立しました。
3.大阪府所在の製造業者の事例
- 調停申立時期
2020年2月 - 裁判所
大阪簡易裁判所 - 権利者(会員企業)
オートデスク インク - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの不正コピーが行われているという情報の提供があったため、上記権利者が上記製造業者に対してソフトウェアのインストール状況やライセンスの保有状況の調査を依頼しました。
その後、製造業者による調査結果を踏まえて、権利者と製造業者との間で損害賠償の交渉を行いましたが、和解交渉がまとまりませんでした。
そこで、上記権利者が大阪簡易裁判所に調停の申し立てを行い、2020年11月に調停が成立しました。
4.愛知県所在の電子部品関連装置の製造販売会社の事例
- 調停申立時期
2017年9月 - 裁判所
愛知県所在の裁判所 - 権利者(会員企業)
アドビ システムズ インコーポレーテッド
オートデスク インク
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの不正コピーが行われているという情報の提供があったため、上記権利者が上記製造販売会社に対してソフトウェアのインストール状況やライセンスの保有状況の調査を依頼しました。
その後、上記製造販売会社による調査結果を踏まえて、権利者と同社との間で不正コピーされたソフトウェアの本数や賠償額について協議を重ねていましたが、和解交渉がまとまりませんでした。
そこで、上記権利者が愛知県所在の裁判所に調停の申し立てを行い、2017年10月に調停が成立しました。
この調停で合意した賠償額は、BSAの通報窓口への通報を端緒とする調停の当時の国内最高額である約1億7400万円でした。
5.大阪府所在の製造業者の事例
- 調停申立時期
2017年5月 - 裁判所
大阪簡易裁判所 - 権利者(会員企業)
マイクロソフト コーポレーション - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの不正コピーが行われているという情報の提供があったため、上記権利者が上記製造業者に対してソフトウェアのインストール状況やライセンスの保有状況の調査を依頼しましたが、同製造業者は一切回答しませんでした。
そこで、上記権利者が大阪簡易裁判所に調停の申し立てを行い、2018年1月に調停が成立しました。
6.兵庫県所在の電気工事業の事例
- 調停申立時期
2017年4月 - 裁判所
尼崎簡易裁判所 - 権利者(会員企業)
オートデスク インク - 事案の概要
BSAの通報窓口にソフトウェアの不正コピーが行われているという情報の提供があったため、上記権利者が上記業者に対してソフトウェアのインストール状況やライセンスの保有状況の調査を依頼しました。
その結果、上記業者においてソフトウェアの不正コピーが行われていることが確認され、権利者と同社との間で不正コピーされたソフトウェアの本数や賠償額について協議を重ねていましたが、和解交渉がまとまりませんでした。
そこで、上記権利者が尼崎簡易裁判所に調停の申し立てを行い、2017年8月に調停が成立しました。
私は、これまでBSA対応に関する案件に多く携わった経験があり、BSAへの対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてBSAとの交渉を行うことが可能です。ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

弁護士 林 邦彦は、企業法務の中でも特に専門性の高い2分野、健康・美容関連商品の広告規制法務と、ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務を得意としております。
薬機法や景品表示法の複雑な規制、あるいはBSAやACCSからの突然の警告といった、企業の存続に関わる重大な問題に対し、約8年間の豊富な経験と深い知見に基づいて、高度で良質なリーガルサービスを提供いたします。
ご相談から問題解決まで、弁護士が一貫して担当し、貴社にとって最善の結果を追求します。
遠方の方でもウェブ会議に対応可能です。 貴社のビジネスの「安心」を全力でサポートいたします。
秘密厳守。お問い合わせを心よりお待ちしております。
BSA・ACCS関連の裁判例紹介(ヘルプデスク事件・コンピュータスクール事件)
ソフトウェアの不正利用に関する代表的な裁判例である大阪地裁平成15年10月23日判決(ヘルプデスク事件・コンピュータスクール事件)をご紹介します。
ACCSによると上記判決は組織内におけるソフトウェアの不正コピーで役員の個人責任を認めた初の判決であり、BSAが公表している資料においても訴訟による損害賠償が認められた事例としてたびたび言及されています(BSAやACCSについては「ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務」というページでご説明していますのでご参照ください)。
なお、上記判決の全文は、裁判所のウェブサイトに掲載されています。
1.当事者
- 原告(ソフトウェアメーカー)
アドビ・システムズ・インコーポレーテッド
マイクロソフト・コーポレーション
クォークインク - 被告(不正利用者)
コンピュータスクール経営会社とその代表取締役
2.事案の概要
被告がパソコン教室等に設置された多数のコンピュータ内に原告らのソフトウェアを違法にインストールした上で、そのソフトウェアを使用してコンピュータプログラムの講習などを行っていた事案です。
原告らはBSA・ACCSの通報窓口を通じて違法インストールが行われているという情報を得て、訴訟提起前に証拠保全の申立てを行いました。そして、被告会社の事務所(パソコン教室を含む)内で実施された証拠保全手続きの結果、事務所内のコンピュータにおいて多数のソフトウェアの違法インストールが行われている事実が確認されました。なお、被告らは、この証拠保全手続きの際に、ファイルを削除などの証拠隠滅行為を行っていました。
その後、原告側と被告側との間で和解交渉が行われましたが、賠償額について折り合いがつかなかったことから、原告らは、会社と代表取締役に対して、損害賠償を請求する訴訟を大阪地裁に提起しました。
また、被告会社は、証拠保全手続後、違法にインストールされたソフトウェアと同一の正規品を購入しました。
3.当事者の主張
この訴訟では(1)違法インストールの数量、(2)原告らの損害額、(3)被告代表取締役の責任の有無が主要な争点となり、損害額及び代表取締役の責任の争点に関して、原告らと被告らは、それぞれ以下のような主張をしました。
原告らの損害額
(1)原告側の主張
- 原告らの「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」(著作権法第114条第2項)について、①プログラムの違法複製による被害の甚大性、②被告会社の行為の高度の違法性、③正規品の事前購入者との均衡、④社会的ルールの要請を考慮すると、正規品標準小売価格の2倍相当額を下らない。
- 著作権法第114条第1項や第2項の損害賠償とは別に、民法第709条に基づき無形損害その他の損害として、逸失利益と同額の損害賠償が認められるべきである。
(2)被告側の主張
- 小売店に帰属すべき小売予定利益まで原告らが受けるべき金銭に含まれる根拠はないため、損害額の算定には標準小売価格ではなく卸売価格を採用すべきである。
- 被告会社は事後的にソフトウェアの正規品を購入しており、それにより損害は填補された。
被告代表取締役の責任の有無
(1)原告側の主張
- 被告代表取締役は、被告会社設置のコンピュータへのソフトウェアの違法複製を自ら行ったか又は被告会社の従業員をしてこれを故意に行わせた。
- 仮にそうでないとしても、被告会社の業務上ソフトウェアの違法複製を行わざるを得ない状況があったのであるから、被告代表取締役に未必の故意又は重過失があったことは明らかである。
(2)被告側の主張
- ソフトウェアの不正コピーはスクールの講師が行ったものであり、被告代表取締役は必要なソフトウェアの管理を講師に任せていて責任はない。
4.裁判所の判断
大阪地裁は、以下のとおり判断した上で、被告会社と被告代表取締役に対して、①正規品標準小売価格相当額(総額約3500万円)、②弁護士費用(総額約350万円)、③遅延損害金の支払いを命じました。
原告らの損害額
(1)原告側の主張について
- 侵害行為の対象となった著作物の性質、内容、価値、取引の実情、侵害行為の性質、内容、侵害行為によって侵害者が得た利益、当事者の関係その他の訴訟当事者間の具体的な事情を勘案すると、本件において、原告らが請求できる「著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」は正規品標準小売価格と同額と認めるのが相当である。
- 原告らは「被告らの違法行為と相当因果関係ある無形損害その他の損害」を何ら具体的に主張立証していないから、原告らの主張を採用することはできない。
(2)被告側の主張について
- 違法行為を行った被告らとの関係で適法な取引関係を前提とした場合の価格を基準としなければならない根拠を見出すことができないため、損害額の算定には卸売価格を採用すべきであるという被告らの主張を採用することはできない。
- 被告会社が支払った金銭は、正規品購入の対価であって、損害賠償債務の履行をしたものではないから、弁済の要件を充たさず、被告らの正規品の購入により損害が填補されたという主張を採用することはできない。
被告代表取締役の責任の有無
- 被告代表取締役は、自らソフトウェアの違法複製を行ったか又は被告会社の従業員がこれを行うのを漫然と放置していたのであるから、被告代表取締役に少なくとも重過失があったことは明らかである。
- ソフトウェアの違法複製の防止に関する管理体制が不備であることは証拠保全手続後の管理体制の強化の点に照らしても明らかであるから、被告代表取締役の故意または重過失を否定する主張は採用することはできない。
5.まとめ
BSA・ACCSに対する通報を端緒として証拠保全、訴訟提起が行われ、正規品標準小売価格相当額に基づき損害額が認定された実例として参考になる事案です。
私は、これまでソフトウェア不正利用の損害賠償対応に関する案件に多く携わった経験があり、BSA・ACCSへの対応に関するご相談をお受けしたり、代理人としてBSA・ACCSとの交渉を行うことが可能です。ご相談をご希望される場合は、問い合わせフォームにてお気軽にお問い合わせください。

弁護士 林 邦彦は、企業法務の中でも特に専門性の高い2分野、健康・美容関連商品の広告規制法務と、ソフトウェア不正利用の損害賠償対応業務を得意としております。
薬機法や景品表示法の複雑な規制、あるいはBSAやACCSからの突然の警告といった、企業の存続に関わる重大な問題に対し、約8年間の豊富な経験と深い知見に基づいて、高度で良質なリーガルサービスを提供いたします。
ご相談から問題解決まで、弁護士が一貫して担当し、貴社にとって最善の結果を追求します。
遠方の方でもウェブ会議に対応可能です。 貴社のビジネスの「安心」を全力でサポートいたします。
秘密厳守。お問い合わせを心よりお待ちしております。